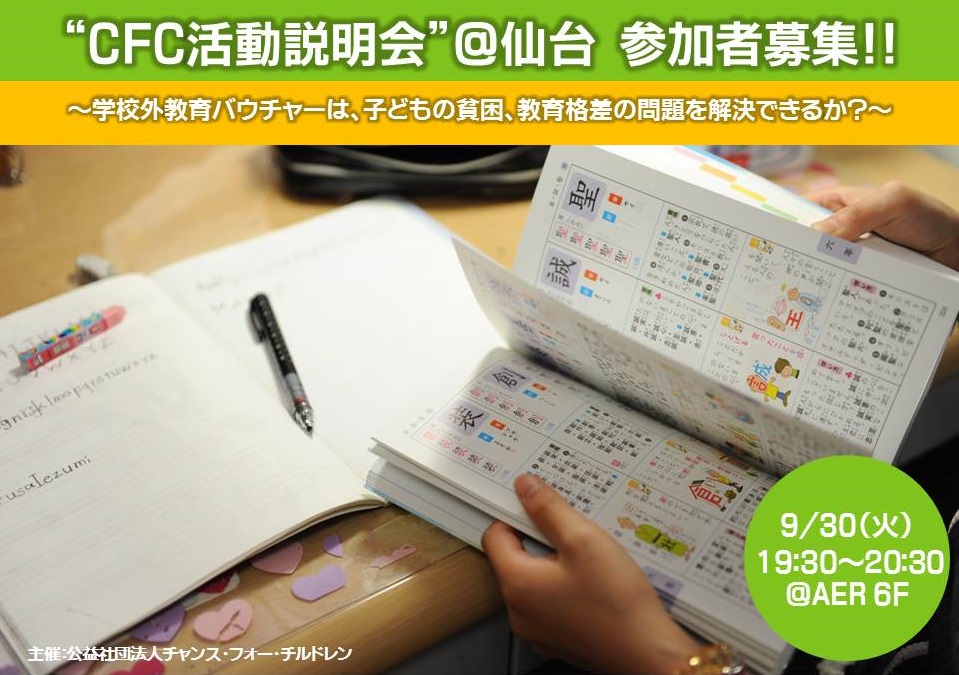
2014.09.26
東日本大震災の発生直後から、宮城県石巻市を拠点に活動を続ける「NPO法人TEDIC」
現在は、石巻の子ども・若者たちの居場所づくりにとどまらず、地域の大人たちも巻き込んでコミュニティづくりに取り組んでいます。
今回は、TEDICで働く奥山悠里さんに、日々子どもたちと接する中で感じる「つながり」の必要性について伺いました。

NPO法人TEDIC 奥山 悠里さん
山形県山形市出身。夫の転勤に伴い、5年前に宮城県石巻市へ移住。子育てをしながら地域で暮らすなかで、子どもと関わる仕事がしたいという思いが強くなり、NPO法人TEDICに入職。現在は小学生から高校生の居場所「ほっとんち」のスタッフとして、子どもたちと同じ目線で楽しむことを大切にしながら、日々活動している。
東日本大震災で地域のコミュニティを失ったことによる「孤立」
東日本大震災で大きな被害があった石巻では、多くの住民が同じ市内で引っ越すことを余儀なくされました。その影響により、これまで築いてきた地域のつながりが弱くなり、特に引っ越した方々は、以前住んでいた地域で代々続いてきたコミュニティから離れることで、元のつながりさえも途切れてしまった状況です。世帯分離や核家族化が進む中で、引っ越した先での新しいコミュニティづくりは難しくなっていることを感じています。
さらに、新型コロナウイルスの影響も重なり、特にひとり親家庭などが地域から孤立しやすくなっていること。震災によるトラウマや、当時十分なケアが行われていなかったのではないかという課題も、地域の子ども・若者と話をしていく中で見えてきています。
拠り所となる居場所を拠点に 地域のつながりを強くする
私たちは、石巻の子どもや若者が地域の大人と出会い、支え合える場をつくることを目的に、地区単位の子どもの居場所「ほっとんち」と、市域全体を対象とした遊び場「レインボーハウス」の2拠点を開設しました。市域全体を対象としたこの取り組みは、ハタチ基金からの助成のおかげで実現した場所です。皆様のご寄付に感謝いたします。
出会いが生まれ、拠り所となる場を提供することで、子ども・若者の支援を進めていくことを考えています。
「ほっとんち」では、地域の大人と子どもが自由に出入りでき、遊びや学び、体験活動を通じて自然なつながりを生み出し、地域の中で顔の見える関係性を育んでいます。
中高生向けに開放している場では、地域の大人や複数の団体・企業、行政が連携し、子ども・若者に必要な支援を包括的に提供する共同体の形成を目指しています。そのために、大人向けの研修や場づくりの体験も実施し、地域全体で子ども・若者を支える力を育成していこうと考えています。

石巻市の子ども支援団体だけでなく、地域の大人も一緒に見守ることで、子どもたちが自分を気にかけてくれる大人の存在に気づく機会が少しずつ広がっています。安心して過ごせる場所で子どもや若者が出会い、そして地域の大人と出会う交差点のような場所にしていきたいです。
一時的ではない支援だからこそ見えてくる“本音”
「人とつながりたくない」と口にする子もいますが、実際には、その子の行動や言葉の端々から、「本当は誰かとつながりたい」という気持ちが見えることが多いように感じます。同時に、大人の側にも「子どもたちのために何かしたい」という思いはあるのですが、その気持ちをどう表現したらよいのか、どこから関わればいいのかを模索している方が多いように感じます。子どもも大人も、お互いに「どこまで歩み寄ればいいのか」を探している。そんな姿を日々感じています。
少しずつではありますが、子ども・若者の居場所から始まる地域のつながりプロジェクトを始めてから、そういった子どもや大人が出会う機会が増えてきました。毎月発行しているカレンダーを見て集まり、大人同士でおしゃべりをしたり、子どもと一緒に遊んだり、気になる子に声をかけて話を聞いたりと、さまざまな小さな関わりが生まれるようになっています。

例えば、これまでは保護者と一緒に過ごしていた子が、他の子どもたちの遊ぶ様子を見て、「混ざりたい」という気持ちを表すようになりました。その思いに気づいた地域の大人が橋渡し役となり、子どもたちの輪の中に自然と入っていけるきっかけをつくったことで、楽しそうに遊ぶ姿が見られました。また、アルバイトの履歴書を書いている子どもに対し、「どんなところを受けようと思っているの?」「頑張っているね」「将来、どんな仕事をしてみたいの?」といった自然な声かけが交わされる場面がありました。その一言がきっかけとなり、働くことに不安を抱いていた子の表情が、ふっと和らぐ様子も見られました。
こうした変化が少しずつ広がっていることを、とても嬉しく思っています。
子どもたちのニーズに応えて開催した非日常空間「ナイトほっとんち」
子どもたちからの「もう少し長い時間開けてほしい」という声をきっかけに生まれた、月に1度開催する「ナイトほっとんち」。夜に、出歩くことの少ない子どもたちにとっては、ワクワクする特別なイベントです。夏には花火やわたあめ作りなどを楽しみました。
初めは、普段「ほっとんち」に通っている子どもたちのために開いていましたが、次第に保護者や兄弟、そして地域の大人たちが仕事終わりにボランティアとして参加してくれるようになりました。

「ナイトほっとんち」では、みんなが同じテーブルに座り、一緒に夕食を楽しみます。普段と変わらない「ほっとんち」の空間ですが、どこか非日常的な雰囲気も漂い、学校に通えている子も通えていない子も混ざり合う場となっています。その中で、「いつから学校に行かなくなったの?」「私は、勉強は好きだけど、学校は苦手なんだ」といった、今の素直な気持ちを自ら話しながら食事をする姿が増えてきました。対人関係で悩んでいた子どもたちも、ほっとんちのなかで友達ができ、少しずつ人と関わることに慣れ楽しく過ごすことができています。
いつでもふらっと立ち寄れる居場所を 今後も開いていきたい
「たくさんの人とつながりたいわけではないけれど、誰かとつながっていたい」と感じる子ども・若者が増えているように感じます。それは、石巻に限らずのことなのかもしれません。子ども支援の取り組みを学びたいという声を受け、能登をはじめとする県外の団体の方々からの視察を受け入れています。また、関東圏に住む高校生や大学生がインターネットを通じてTEDICの活動を知り、「石巻や震災について学びたい」と関心を持ってくれることもあり、他地域でもこの取り組みが必要とされていることがわかります。
石巻は交通の便が悪く自宅から通うことが難しい子どもたちに向けて、「石巻圏域子ども・若者総合相談センター」の相談員と一緒に訪問支援も行っています。その際、子どもたちを「ほっとんち」や「中高生向けの遊び場」に誘いますが、「今は大丈夫」「行きたくなったら行くね」と答え、家の中で過ごす子が多いのが現状です。予約なしで気軽に来られる場所です。自分のペースで外に出るきっかけがつかめるように、これからもいつでもふらっと立ち寄れる居場所を開き続けたいと思っています。